物心ついたとき、既に親も、兄弟の顔も知らなかった。
だけど、兄弟と呼べる人間はいた。私は彼を兄と慕っていた。
同じ施設で育った、三つ年上の男の子。
施設の大人たちからは乱暴者で反抗的と、決して芳しい評判の少年 ではなかったが、対照的に内向的で泣き虫だった私をいつも庇ってくれ た。
どんなに大人たちの命令に従わない乱暴者でも、それでも私への悪意に 対してはいつも必死になって守ってくれた。苛められている私を見て、 喧嘩騒ぎを起こしては生傷をいつもこしらえていた。
お前のためだ――。苛めっ子を追い払い、傷だらけになった彼はいつも 口癖のようにそう言ってくれた。
幼い少女だった私は、そんな言葉と共に、いつもはにかんで見せる彼の 笑顔が好きだった。
物の分別が付き始める頃になって判ったことだが、私たちのいた 養護施設は政府の直轄下にあった。それも、政府の手駒としての プロフェッショナルたる人材を育てるための。
同じ年頃の子供たちが教えられる知識、教養と共に、私たちが叩き 込まれたのは政府への忠誠と、各々の個性に合った特殊技能の修得だった。 私は諜報関係の才覚を養成、件の、三つ年上の少年はその戦闘的性質から 兵士としての技能を求められた。
幸か不幸か、私たちはお互い大人たちの要望に足る能力を開花 させてみせた。各々の個性に準じた能力を育てるという、大人たちの思惑は 一応成功と言えるだろう。しかし、私たちの忠誠は、決して政府には 傾かなかった。
私も彼も、疑問に対して妥協できる性格ではなかったということもある。 何より兄として、妹として、お互い支えあって生きてきた私たちにとって、 信頼に足る存在はあくまでお互いのみだったのだ。
私たちを利用することしか考えていない大人たちに、何を服従する意味が あるというのか。
いつの頃からか、兄と呼ぶ彼は反抗の野心を抱くようになっていた。いつか必ず、自分たちを利用しようとする連中の度肝を抜いてやる。そんな強がりとも取れる言葉を、私は何度傍らで聞いただろう。 そうして互いにそれぞれの能力を生かせる部署に配属され、表向き政 府の有能なる手駒として活動を始めた頃、彼の、とある組織と接触を持った という独白に、私はついに…という動揺を隠せなかった。
その時すでに私たちは、小笠原の秘密施設を拠点とする、政府の最重要 機密に関わる要員にまで上り詰めていた。パイロットとして、作戦指揮官 候補として、それぞれ優秀なる能力を発揮して見せた故の居場所である。
ここまでに至ったその時が、彼がその野心を目覚めさせる、待ち望んでいた 瞬間でもあった。
小笠原にて行われている最重要機密。詳細は掴めないが、それは既存の 兵器概念を一新する新兵器の開発にあった。
新兵器、コードネーム"サイバー・ゼロ"。
彼はそのテストパイロットとして、私はその新兵器による作戦指揮官 候補として抜擢されるまでになっていたのだ。彼の計画には、私たちが そこまでの要職に至ることが重要だった。
そう、この計画は、この私自身が一枚噛んで成立する物だったのである。
ICON。それが彼が接触を持った組織の名だ。彼からの独白を受け、 私は独自にこの組織について洗ってみた。しかし、残念なことにはっきりと した成果は掴めなかった。
並み居る軍事テロ組織を遥かに凌ぐ武力と、驚くまでに巨大な組織力。 そして組織としてはかなり古い歴史を持っていること。そんなにも巨大な 組織に関わらず、政府の情報ネットワークを駆使してもそれ以上の情報を 知り得ることはできなかったのだ。そしてこの組織は、彼が動かすことと なるサイバー・ゼロを欲している。
この計画の成功には、莫大な報酬と私たちの生涯の自由が約束されていた。 しかし、私はこの計画に抱いた不信感を拭うことができなかった。 サイバー・ゼロ、そしてICON、両者の正体があまりに不明すぎるのだ。
そう、ICONと並んで探りを入れたサイバー・ゼロについても、私は その概要以上の正体を掴みあぐねていた。
全長27メートルに及ぶ、巨大人型多肢兵器――。如何なる戦略思想上に よる産物なのか、驚くべきことにそれは"人の形を模した兵器"だった。
全身を循環する液体金属の圧力制御による駆動系。同じく液体金属の 比重移動による、まさに生物的な稼動を実現させる重心配分機構。硬度かつ 精密なできのマニピュレーター等、それらの全ては、確かにICONなる 組織ならずとも欲しがるであろう、既存の多肢機械工学の最高水準の 結晶体と言えた。しかし何故か、その動力源、制御系という最重要な部分の 情報まで掴むことはできなかった。
その理由は明白だ。どんなに機密の奥深くまで調べを入れても、この名が 出て来たところで情報は行き詰まってしまう。そして、調査上始めてこの名が 出てきたとき、私は軽い驚きを覚えた物だ。
西皇浄三郎。齢90を越える老人ながら、なおも政府、政財界に強い影響力 を持つ"この国の影の支配者"とも揶揄される怪老だ。そして、この老人こそ が私たちの配属された小笠原の秘密施設"十字の檻(クロスケイジ)"の理論 指導者であり、同時に私たちの育った施設の出資者だった。
西皇の名に、私は不安を隠せなかった。揶揄される通り実質上この国の 影の指導者とも呼べる西皇が、その心血を注ぐサイバー・ゼロ。私の兄でも ある彼は、推し量ることもできないその巨大な力を、更に正体不明の巨大な 組織へと売り渡そうとしている。
謎の組織ICONと西皇の関係は不明だ。しかし、このあまりに巨大すぎる 存在の狭間に彼は――私たちは飛び込もうとしている。そのリスクは比例して 大きすぎる物だ。
そして、私の不安を増やす要因がもうひとつあった。サイバー・ゼロに ついて調べえた情報のひとつとして、サイバー・ゼロに関わった要員の何名 かが謎の失踪を遂げている。しかも、それは彼同様のテストパイロット、 あるいは制御系の開発要員という極めてサイバー・ゼロの秘密に近付いた 者達だったのだ。
私はその事実を踏まえての不安を彼に訴えたが、そんな私の言葉を彼は 一笑に付した。
確かに狙う相手は危険かつ大きすぎるかも知れない。しかし、計画に おいては身に危険が及ぶ前にサイバー・ゼロごと例の組織に投降できる。 それに相手が大きければ大きいほど、危なければ危ないほどこの計画は 価値あるものとなる。私たちが、初めて手にする自由のために。
その時私は、彼の気持ちが判らなかった。
私は正直、この計画などどうでもよかったのだ。若干の不都合はあろうと、 今現在の地位は私に今後の生活、人生を保障してくれていた。それは彼に とっても同様のはずなのだ。
利用されることは我慢ならないかも知れない。だけど、生きていく上での 妥協は必要のはずだ。利用したいと言うのなら、せいぜい協力してやれば よいではないか。協力してやった分の代価を保証してくれるのならば。 そして私たちは、その代価を充分求められる位置にまでたどり着けたのだ。
しかし、そんな私の思いに、彼は激しく激昂した。
お前はそれでいいのか。そうして他者に利用されていくのが自分たちの 人生か。そんな恣意と妥協にまみれた一生を送っていく気なのか。
一体、お前の自由は何処にあるというのだ。
私は、おそらくは彼よりも大人になっていたつもりで、その言葉に応じた。 自由は、束縛の中にしかないと――。
そして彼は、なおも強い口調で告げた。
すべては、お前のためだ。
…その言葉が、嬉しくなかったと言えば嘘になる。それは子供の頃から、 いつも、私を支えてくれた言葉だった。
だけど、私はその時、反射的に叫び返した。
"私のため"という言葉で、私を縛るのはやめて――。
私を縛っていたのは、決して政府などではない。心の奥で、自分でも知らず に私はそれに気付いていたのかもしれない。思い返せば私はいつも、 常に彼の言うがままに生きてきていた。彼のその行為は、いつもこの言葉と 共に私の中で正当化されていた。私のためだというひと言に。
いつの間にか、私はその言葉に反発を抱くようになっていたのだ。 もう私は自分で人生を決められる。それなのになお彼の言うがままに生きて いく必要がどこにあるのか。
しかし、私の思わぬ叫びを受けてもなお、彼は決意を変えなかった。 たとえ私の協力を得られなくともサイバー・ゼロ強奪を諦めるつもりは なかったのである。
彼が打ち明けた計画はこうだ。サイバー・ゼロの稼動実験が富士の演習場 にて、機体を小笠原から移動して行われる。その際、乱入してくるICON 側にサイバー・ゼロに乗ったまま彼は投降。同時、その時オブザーバーとして 実験に立ち会う私が指揮所を占拠、実験データをも強奪するという手筈 だった。
私の役割に関してはさほど問題はない。一端のエージェントとしての訓練は 幼い頃から叩き込まれている。自らの戦闘的技量には確かな自信がある。 問題はあくまで、強奪する機体と投降する組織が正体不明過ぎる点だ。
だが、本音を言えばそれだけではなかった。例の行方不明者の件もあるが、 不確かながら…言い知れぬ不安があった。できればそんな無謀な計画など 忘れて、実力で勝ち得た今の地位、今の世界を上手く渡って生きていって ほしかった。
適度に利用されてやるぐらいの妥協が何故悪いのか。
"私のため"という言葉を使うなら、なぜ、私の気持ちを考えて くれないのか。
実行前日、最後の説得のつもりで、彼にそう訴えた。
私の、そんな言葉に、彼は応じてはくれなかった。とうとう最後の最後 まで、私は彼の決意を変えることはできなかった――その自身の非力さが 胸に突き刺さった。
そして唐突に、私は彼の手に、これまで集め得たサイバー・ゼロに関する 全てのデータを押し付けた。
やや面食らった顔の彼に、私は、搾り出すように、唸った。
これで、終わりにしよう、と
私と彼の別離の日が来た。
小笠原の"十字の檻"からこの富士の裾野に運ばれ、屹立するサイバー・ゼロ の姿に、データ上の存在しか知らなかった私は軽く畏怖を覚えた。
やはり実際に身長30メートルに達する人型の巨体を目の当たりにするのは、 それだけで何処か圧倒される雰囲気がある。その巨体に、更なる禍々しさを 感じさせるのが、如何なる兵器的思想で付けられたのかも判別しかねる 胸の獣面だ。
獰猛な肉食獣の顔面を模したその獣面を見るにつけ、私は前々からの 不安感が更に募る思いがした。
その外見だけではない。やはりこの機体は――どこか危険過ぎる。
鉄筋の指揮所には、サイバー・ゼロの開発責任者である"十字の檻"代表、 斬馬博士が幾名ものスタッフの中心となって指示を飛ばしている。 そのスタッフの中には、やはりサイバー・ゼロ開発スタッフである三枝博士の 他に私を驚かせる人物がいた。
実質上、サイバー・ゼロを作らせた男、西皇浄三郎である。
指揮所の大窓からはサイバー・ゼロが立ち尽くす演習場が一望でき、 各実験データを表示するために設置されたスクリーンの一角には、サイバー・ ゼロのコクピットに座る彼の映像もあった。
実験開始を待つ、やや緊張したという面持ち。しかしその胸中の真意を 知る者は、私田だひとりなのだ。
彼ばかりでない、指揮所のスタッフたちも皆、実験開始を前に慌しくも 緊張した雰囲気に包まれていた。しかしそんな雰囲気の中にあって、流石 というか、部屋の中央に居座った西皇だけは、その年齢を感じさせない 凛々しい唇の端に、余裕とも取れる笑みを浮かべていた。
実験開始の時は来た。斬馬博士の指示により、指揮所からサイバー・ゼロの 全システムが起動させられる。
大窓から覗くサイバー・ゼロの、その頭部の双眸に起動を示す光が宿り、 コクピット内の彼に対し斬馬博士が指示を送る。
異変が起こった。
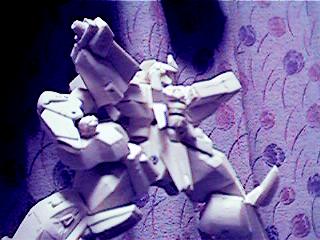
まずは簡単な歩行から開始するはずのサイバー・ゼロの機体が、一歩たり とも動こうとはしないのだ。その直線的なラインで構成された装甲が小刻み に震え、機体の各部から微かな火花が散っている。
何事かとスクリーンに目を走らせた、指揮所内の一同の視線が固まった。
私は、声を出しそうになっていた。スクリーンに表示される機体情報は 機体の異常を激しく訴え、その一角に映る彼は、絶叫を上げていた。
彼の身体が…崩れ始めていた。
いや、崩れ始めたという形容が当てはまるのかどうか。その身体が淡い 白光に包まれ、それが肉体を侵食、分解していくかのごとく周囲に光の粉を 撒き散らしている。
その全身を包んだ光に、文字通り、やはり光の泡粒となって彼の身が 削られているのだ。
思わず目を背けたとき、大窓の外のサイバー・ゼロに視線が行った。 その胸部の獣面の顎が蠢動しているように見えた。
"何かを喰らう"かのように。
またか…。
三枝博士の、その冷徹な美貌に似合わぬ舌打ち混じりの呟きを私は聞き 逃さなかった。
コクピット内部を映す映像の中で、彼の左手が光の粒子となってついに 宙空に溶け散った。まだ溶けずに残っている目が、自らの左手のあった辺り の空間を茫然と見つめている。
彼は"喰われて"いた。
後になってから、私はこれまでサイバー・ゼロの中枢に関わった人間たちが 謎の消失を遂げた理由を悟った。テストパイロット、制御系の技術者、 彼らは皆、同様にサイバー・ゼロのコクピットの中に収まり、そして" 喰われた"のだ。
サイバー・ゼロの中枢に対しての、激しいまでの情報のプロテクトも今と なっては理解できる。
こんな危険な機体を、一体西皇浄三郎は何のために使おうというのだ。
そして、指揮所を新たなる衝撃が襲った。
あまりに突然に、襲撃が来た。
おそらくは遥か上空を行く航空機から降下して来たのだろう、それは一瞬、 重武装に身を包んだ二名の降下兵に見えた。しかしその存在をはっきり 認識したとき、私は目を疑った。
如何なる意匠か、頭部にある本来の顔面の他、腰部の前面にもまるで悪鬼の ごとき意匠のマスクを備えたそれは、ほぼサイバー・ゼロと同程度の体躯を 持つ――サイバー・ゼロ同様の巨大人型多肢兵器。
ICONか。斬馬博士がそう唸るのが聞こえた。
では、あれが謎の組織ICONの物だというのか。こちらがサイバー・ゼロ 一体をまだ完成に至らしめていないというのに、あの組織は、すでに サイバー・ゼロ同様の兵器を作り上げているというのか。
何より、あれだけのものを既に兵力として保持する組織が、何故にいまさら サイバー・ゼロなど欲するのだ。
ICON機の一機が、震え、全身のあちこちから火花を散らすサイバー ・ゼロに背中から抱きついた。どうやらそのまま機体を持ち去る算段らしい。 そして、残るもう一機が手にした銃器を私たちのいる指揮所に向ける。
銃器といっても、巨体の持つそれは既に艦砲と言って差し支えないスケール の代物だ。鉄筋とはいえこの程度の指揮所など、一撃で吹き飛ばされて 終わりだろう。
その場に固まった私たちは、ひと言もなく窓の外の、火器を構える巨体を 凝視していた。数瞬後には確実に訪れる死、それへの確かな自覚も抱けない まま。
と、
ギギ…、もう一機の巨体に抑えられたサイバー・ゼロが、その機体を軋ませ た。何事か、全身から飛び散る火花もその激しさを増したかに見える。
刹那、サイバー・ゼロの機体から銀色の液体が噴き上がった。まさに サイバー・ゼロの体液とも言える、全身を循環する液体金属だ。それが装甲と 装甲の隙間と言わず、機体中の間接部分からも、まさに全身から鮮血を跳び 散らすがごとく噴き上げているのだ。
バキッ、金属が激しく引き千切られる音が響いた。サイバー・ゼロからでは ない、その機体を抑えつけた、背後の敵機からだ。そのICONの機体から 右腕が引き千切られ、勢いで後方に飛び、ユーモラスなまでに地に尻餅を 着いている。
引き千切られた。一体何者に。私のその疑問は即座に明かされた。
指揮所のあちこちから、おおという感嘆の声が上がる。サイバー・ゼロだ。 その巨体が、自らを縛る戒めを解くため、初めて"動いて"みせたのだ。
サイバー・ゼロから距離を置き、それぞれ火器を向ける二機の敵機。その 二機の目前で、サイバー・ゼロに異変が起こった。
全身からの液体金属の漏れが止まり、身体中から金属が砕ける音を響かせ、 その機体が奇妙に膨れ上がっていく。本体の変化に合わせるかのように、 直線的だったその装甲も、ボコボコ…と沸き立つようにいびつに 歪み始める。
サイバー・ゼロに一体なにが起こっているのか。先までの直線的かつ 整然とした、まさに機械的な表貌が、腰を曲げ、爪を立てるという、 その人間の姿勢を攻撃的に突出させた、まるでいびつな鎧を被った一個の 生き物のようにも見える。
その胸部の、異形の獣面が牙を剥き、大きく金属的な咆哮を上げた。 それだけで一歩退く二機。
その咆哮に一瞬我に帰り、私は再び、彼のいるコクピット内を映した スクリーンに目を向けた。何故か、現実感もなくそれを虚ろに見つめる。 そこに居るのは、四肢も完全に溶け落ちた、既に肉塊とも形容できない 光の粉を散らす物体だ。
だが、その目は、まるで敵に噛み付く獣のごとくぎらぎらと輝き、視線は 一方を見つめて凝固している。 その視線の先に、私のいる指揮所があることに、私はその時気付か なかった。
そして――口元が、声に出ずとも僅かな言葉を刻んでいるのが見えた。 私は唇を読んだ。
…オ、マ、エ、ノ…タ、メ、ダ…、
グォォォッ、再度咆哮を上げ、ついにサイバー・ゼロが二機に 挑みかかった。爪立った掌が、先ほど右腕を引き千切った方の機体の顔面を 掴み上げる。そのまま敵機を力づくで押し倒しつつ、掴んだ頭部を地面に 叩きつける。まるで野菜か何かのように容易く爆ぜ、砕け散る頭部。 更に手を組み、倒れた機体の腹に勢いをつけて振り落とす。強烈なハンマー の一撃となり、それだけで上下に分断される機体。爆発――。

残った一機が、怯えたかのように沸きあがった爆炎の中へと銃弾を 撃ちまくる。瞬間、その炎の中から、当の敵機へと飛び出すサイバー・ ゼロ。
更に銃を撃つICON機。装甲を掠める銃弾の一発が、その凶獣の左腕を 肘から千切り飛ばす。だがサイバー・ゼロの突進は止まらない。
サイバー・ゼロの右手が左腕の傷口を掴んだ。刹那、驚くべきことが起こる。 傷口から噴出す液体金属が急速に収束、そのまま長大な刃物の形状へと 固まったのだ。
それは、斧だ。おそらく、ひと目で斬れぬ物はないと感じさせる、呆れる ほど巨大な斧――。
――斬、 右腕一本で揮われた斧の一閃、振り下ろされた斧が地面に深く突き 刺さる。
頭頂から一気に、あまりに鋭利に両断されるICON機。その両断された 機体が地に倒れる前に、炎が上がった。四散する機体。
…誰もが、ひと言もなく、目前の凄惨な光景に茫然となっていた。私は、 その光景から目を背けるように、あのスクリーンをもう一度見た。
そこにはもう、光の粒も、光の粉を散らす物体も何もなかった。
コクピット内を映す映像には、先までそこに人が乗っていたことなど 感じさせない、無人の機械的、無機質な空間だけが映し出されていた。
私は、ただじっと、そのスクリーンの隅の小さい映像を凝視していた。
哄笑が響いた。
ひと言もない指揮所の中、ただひとり、西皇浄三郎の歓喜の哄笑だけが 高く響いていた。
西皇によって、サイバー・ゼロに"破導獣斬砕刃(ザンサイバー)"の名が 与えられたのは、それから間もなくのことである。
二年後、内部構造、装甲を徹底的に修復し、サイバー・ゼロは改めて ザンサイバーとして完成。完成と同時、斬馬博士、ザンサイバーを強奪。
ザンサイバーに"喰われる"ことなく動かすことの出来る資質の持主が、 斬馬博士の血族の人間と判明。指示により、私の指揮下にて斬馬博士の 子息、弦少年を含むザンサイバー奪回部隊を編成、機体の消えた 日本アルプスへと向かう。
最終目的どおり、斬馬 弦をザンサイバーに乗せることに成功。ICON の突然の襲撃を受けつつ、ザンサイバー、初戦にてこれを撃退。
私の兄はザンサイバーの中に消え、そして、斬馬 弦は生き残った。
だが、私は、あの時感じた言い様のない不安をまたも感じている。 正式な"飼主"としてあの凶獣を飼い慣らしたとはいえ、果たして ザンサイバーに関わることで…斬馬 弦、彼の運命はどう豹変していくの だろう。
ザンサイバーの、人の手に余るままならない禍々しさに、これから 斬馬 弦はいやがおうにも直面することとなる。
――あの悲劇以上のことが起きるというのか。私は内心の、その恐怖を 拭いきれない。全ての真相を知ることなく、あの少年は悲劇の渦中へと 巻き込まれようとしている。
いや、巻き込まれたのではない、"縛られた"のだ。あの少年も、私の兄も、 そして、おそらくは私もまた…あの鋼の血を流す凶獣に。
果たして誰が、生きたままこの堅く重い、鈍い銀色の血の呪縛から 逃れられるというのだろう。
「あなたも…喰われたほうが幸せだったのかもしれないのに」
縛られた中、少なくとも、苦しみからは自由になったあの人のことが思いを よぎり、私は泣いた。